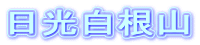
ゴンドラ山頂駅より望む日光白根山
冬になると思い出す日光白根山
えっ、日光白根に行くの?という家族の冷ややかな雰囲気を乗り越えて行って来ました
02年12月14日(土) 快晴 単独
日光白根山 2,578m
丸沼スキー場山頂駅〜大日如来〜樹林コース〜山頂〜弥陀ケ池分岐〜七色平〜山頂駅
10:00 10:40 12:55-13:25 15:30
数年前の冬に湯元から山頂をめざした。しかし視界不良のため下山時に道に迷いみんなに迷惑と心配をかけてしまった。わが山歩きの最大の失敗であった。それ以来日光白根山はトラウマになっている。しかし、この山に登ると「安全な山歩きをしなければ!」との思いがよみがえるようになり、私の山歩きの安全確認に欠かせない冬の行事である(^^;;;
今日は天気がよいとの予報。この冬はまだ雪山歩きをしていない。ならばこの冬の安全登山を祈願しに登ろうと決めた。しかし1ケ月程山歩きをしていないので湯元からは厳しい。ゴンドラでラクチンな「丸沼高原スキー場から」登ることにした。
ここは夏に一度登ったことがある。ゴンドラで一気に標高2,000m迄運んでくれる。しかしその後は結構厳しい斜面もあり、果たして雪のある時期に登れるのか不安もあった。まあ、ダメだったら付近のスノートレッキングでもいいや、無理は禁物。何しろ関東以北で最高峰の山だから…
ゴンドラは8時半運転開始らしいのでのんびりと家を出発。しかし鎌田あたりでとんでもない渋滞に巻き込まれた。遅々として進まない。少し前に救急車が走っていったのでたぶん事故だろう。反対車線も殆ど通行車がこない。もう絶望的(^^;;; しかここはナビゲーターという今日な武器がある。迂回路を探し横道に突入。同じ様な車が数台。安心して付いていったら、なんと行き止まり。カーナビでは少し手前を曲がるように指示が出ていたが、機械より人を信用した私が間抜けだった。
いやあ、参ったねと言うような顔で皆Uターン。今度こそナビを信じて迂回する。そしてスキー場に着いたのは9時半だった。今日は大入り満員のようで駐車場も混雑していた。ゴンドラ切符を買う。1回券が1,200円。下りはどうするか分からないが、もしくたびれたらゴンドラ利用としたい。上でも切符売っているのかと問うと、どうも要領を得ない。確認した結果、下りは1回券を買っておけば乗れるらしい。改札は結構混んでいたが、高速のため以外と順番が早く来た。自動改札では券は回収されてしまった。あれっ、本当に下りに乗れるのかなあ?券が無くっても大丈夫なんだろうか?
ゴンドラは一気に標高を2,000mまで迄運んでくれる。いやあ、ラクチンラクチン。こんなに楽して冬山に登っていいんだろうか(^^;;; 山頂駅からは青空の中に白根山が聳えている。はやる気持ちを抑えて日焼け止めを塗る。登山コースへとトレースも続いている。登山届けのポストは投函口の扉が開いて雪がたまっている。そこには登山届けは一枚も入っていなかった。果たして先行者は近くのハイキングのみだろうか?とすると、山頂までは厳しいかもしれないなと、届けを投函しなだらかな樹林帯を進む。
 |
 |
| ゴンドラ山頂駅より望む白根山 |
登山ポスト |
このコースは夏に歩いたことがあるが、やはり積雪があると様子が一変する。トレースは続いている。ちょっと歩きにくいがまだスノーシューは不要だ。先行者は複数の感じだ。大日如来までは緩やかな登り、そして樹林帯のため展望は良くない。時々トレースを外すとズボッと股下位まで埋まる。大日如来は雪に埋まって見えなかった。そのあたりから眺める白根山は堂々としている。もう少し登ると厳しい急登が待っている。果たして山頂までたどり着けるだろうか…
 |
| 大日如来付近の積雪 |
このあたりから樹林越しに展望が少しづつ良くなってくる。避難小屋への分岐を過ぎると徐々に登りがきつくなってくる。途中、「この先崖崩れの恐れあり、安全の為迂回して下さい」との標識があった。見るとわずかにトレースがあるが、だいぶ以前のもののようだ。数人のトレースは右に回り込んでいる。結構回り道になりそうだが、今日は安全祈願の登山である。指示通り迂回する。トラバース気味に少しずつ高度を上げる。樹林の間からは尾瀬の燧ケ岳や上州武尊山が望まれる。登りがきつくなる。久しぶりの山で息が切れる。まだトレースは続いている。ここまであると言うことは、先行者は山頂をめざしていることは明白だ。よし、これなら山頂は問題なさそうだ。
 |
| 上州武尊山を望む |
時々、ズボッと埋まる。股下あたりまで埋まると抜け出すのはやっかいだ。少しづつ手袋が冷たくなってきた。しかし今日は暖かい方だろう。まだオーバージャケットは不要だ。徐々に登りがきつくなる。地形図から見てもう少しで樹林帯を抜けるはずだがと思っていたら一気に樹林帯を突破して開放感溢れる広場に出た。前方の山肌に7名くらいの集団が休んでいた。どうもアイゼンを付けているような雰囲気だ。ここらあたりから少し雪が固くなってきたが我が輩はまだアイゼンはない方がよい。ピッケルもまだ不要でダブルストックの方が歩きやすい。雪は風で飛ばされるのかそれほど積もっていない。
 |
 |
| 樹林帯を抜けると開放感のある景色が |
窪地までもう少し |
風が強い。でも防寒具を着るほどでもない。足下に気を付けて慎重に登る。そして以前夏にツエルトで泊まった事のある窪地に到着した。ここは道に迷って迷惑をかけた翌年の夏、怖い思いに駆られながら夜を明かしたところだ。あのときは物音一つしてもビクッとしたものだ。
そして祠の先からいったん下り、わずか登り返すと山頂である。先ほどの団体さんが記念撮影を撮りおえ下山準備をしていた。どうもガイド登山のようだ。お客は皆中高年の女性。ガイドらしき人は二名いた。この団体が下ったあとは大展望を独り占め。富士山も見えておる。、もちろん尾瀬の山々は手に取るようだ。筑波山も見えている。ど〜んと構えるのは日光連山だ。以外と日光男体山は雪が少なそうに見える。今度は雪のある時期に登ってみたいものだ。
 |
| 山頂から望む日光連山。眼下は五色湖、右奥が男体山 |
前方の弥陀ケ池へ下る方のピークに2名が休んでいた。あの人達はどちらに下るのだろう?団体さんはピストンだし、二人は登りで全然見かけなかったからたぶん菅沼の方から登ってきたんだろうと憶測する。我が輩は予定では弥陀ケ池への分岐から七色平のコースを予定していた。たぶんトレースはないだろう。下山コースは夏に歩いたこともあり、登りの状況から見てもトレースが無くとも下りだし大丈夫だろう。それにこの天候、急変はなさそうだ。時間もまだ余裕がある。「よし、予定通り下ろう」と決定。
 |
 |
| 下山を始めたグループ |
山頂独り占め |
念のため温存していたGPSをしっかりセットする。以前この山で失敗したときは、何度も登った山との安心感からガスっているにも関わらず磁石による確認を怠ったことが最大要因だった。今日は快晴だが用心用心(^^;;; 弥陀ケ池への下りは一部急な岩場がありちょっとビビった。まだアイゼンやピッケルは準備していなかった。ザイルもザックの中だ。しっかりと足場や手がかりを確認し慎重に時間をかけてクリアーする。ホット一息だ。これで今日の最大の難所は通過。あとはひたすら下るだけだ。眼下の弥陀ケ池に先ほどの2人組が見える。おや、もう一人居るようだ。そこで待っていたのかなあ。眺めていると、やはり菅沼方面へ歩いていった。
途中から坪足では歩けないほどもぐるようになった。ここでようやくスノーシューの出番だ。そう言えば山頂では展望に見とれて昼食を取るのを忘れていた。この先は樹林帯となるのでここで一休みして腹ごしらえしよう。今年初めてのスノーシュー、なんか緊張するなあ(^^;;;
急な下りはスノーシューは苦手だ。思い切って尻セードで滑る。いやあ、面白い。と調子に乗っていたらもっこりした岩の出っ張りで思いっきり尻を打った。まあ、雪がクッションになって大事なところは大事に至らなかったが、良く地形など見てくだらないとやばいなと思った次第です。そして弥陀ケ池への分岐に到着。いよいよここからはトレースのない道となる。GPSで慎重にルートを確認。樹林帯で薄暗い下りはちょっと心細い。スノーシューを履いていても歩くより滑る方が良さそうな急な下りが何カ所か出てくる。わずかだがテープもあるので、それを見逃さないように下る。雪に隠された岩の窪みや木にスノーシューを引っかけて何度も転んだ。その度に雪だるまのように真っ白になってしまう。
以前迷ったときも同じように雪だるまになったが、その時とは全然違う心理状態。今日は楽しい!あのときは心細いし、悪い方へ悪い方へと考えが揺れる。このまま雪に埋もれてしまうのでは無かろうかと…そんなことを思い出しながら下る。トレースはないが何となく道らしい光景は樹林の状態や、雪の窪みの状態から判断できる。これもゆとりがあるから出来ることだろう。いざというときにも慌てず騒がず、慎重に周りを見つめることが大事だなと思った。
 |
 |
| 結構急な下りもあった |
避難小屋 |
そして七色平への分岐に到着。七色平から避難小屋付近はだだっ広い場所であり、迷わないように細心の注意が必要だ。小屋から先も分かりにくい。ここらあたりから右手に曲がらなければとちょっとよいしょっと尾根をのっこすと登りに歩いたコースの合流した。ここからはトレースもありわずかでゴンドラ山頂駅に到着した。切符がなかったので不安だったが、なにも言わない内から「さあ、どうぞ」と係りの人がゴンドラへと案内してくれた。やはり1回券で良かったんだなと安堵。登りも下りもラクチンゴンドラで快適な日光白根山の雪山登山は終了した。
明日も天気が良さそうだ。谷川岳へ行こう!と思いながら帰路についた。
おひるねの森へ 戻る
![]()
